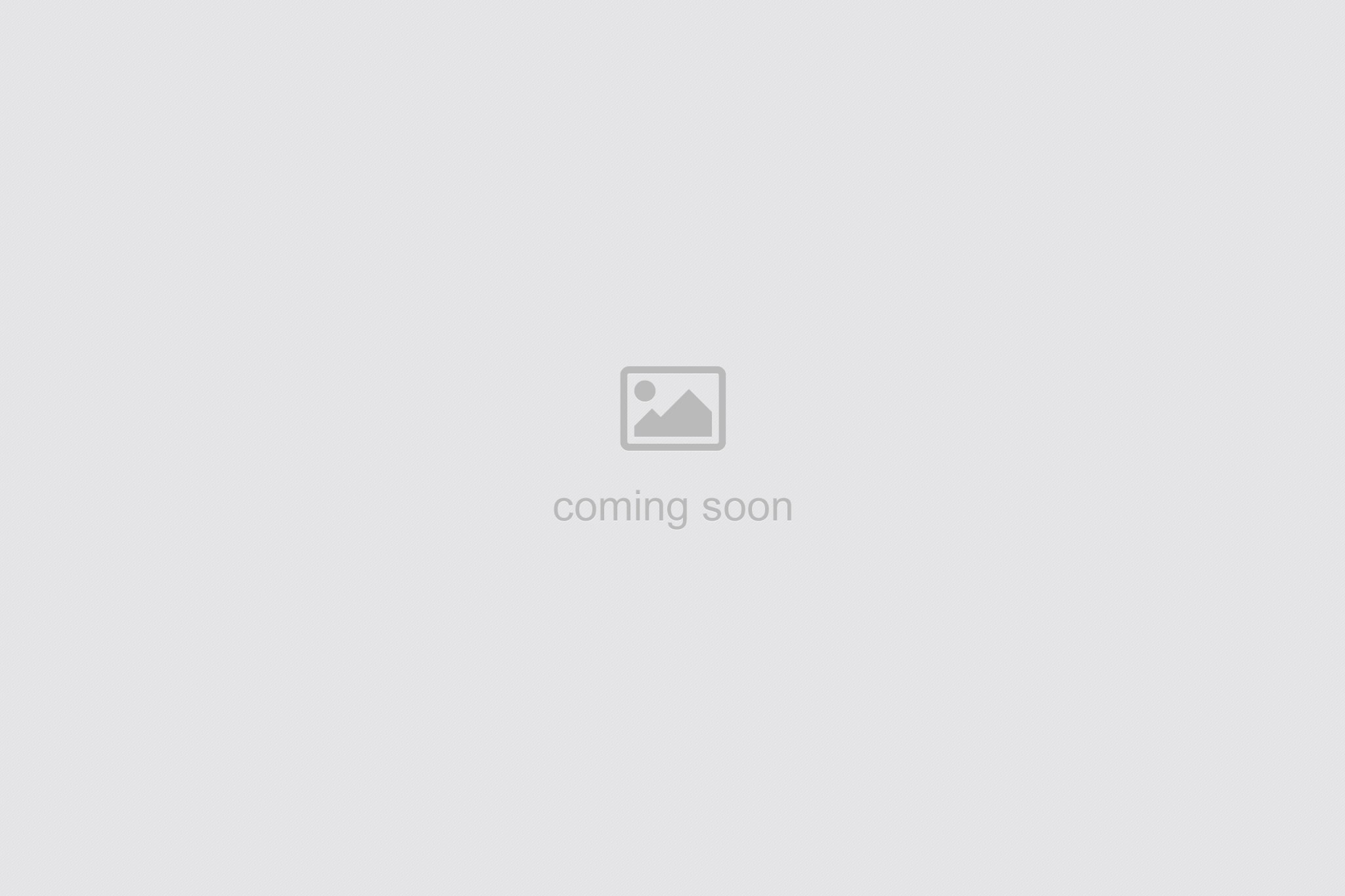毎月発行される香川県建設労働組合の機関誌「香川建設ユニオン」において、保健師による健康に関する記事を連載しています。
こちらでは、過去に掲載された記事をご紹介しています。
こちらでは、過去に掲載された記事をご紹介しています。
令和7年4月号に掲載
2025-04-10
【保健師だより】高尿酸血症
プリン体は、食品から摂取するものが約2割、細胞の新陳代謝やエネルギー代謝によって作られるものが約8割とされています。このプリン体が肝臓で代謝されると尿酸に変わります。
高尿酸血症は、血液中に含まれる尿酸が1dlあたり7mgを超えた状態を指し、7mgを超えると、関節の中で尿酸が溶けきらずに結晶化していきます。尿酸塩結晶が、なにかのはずみで剥がれると、炎症がおこり、激しい痛みや腫れが生じます。結晶は、関節の中でも膝から先の関節に溜まりやすく、特に足の親指の付け根は負荷がかかりやすく、冷えやすいことも要因となって痛風発作が現れやすくなっています。その他、足の甲、足首、くるぶし、手の指、手首、肘などでも痛風発作が起こることがあります。
また尿酸値が高い状態が長く続くと結晶が増え続け、足の親指や膝、肘、耳などにコブのような痛風結節ができるようになります。放置すると動きが悪くなったり、変形することがあります。それ以外にも、尿路結石や慢性腎臓病を合併しやすくなります。
尿酸値を上げないポイント
①適切なエネルギー摂取
肥満度や体脂肪率が高いと、それに伴い尿酸値も高くなります。
②プリン体の多い食品を摂りすぎない
レバー、白子、干物は特に多く含まれています。
③飲酒を控える
アルコールは、体内で代謝される際に尿酸を過剰に作るため、飲酒量が多いほど尿酸値が上がります。
④果糖の多い食品を摂りすぎない
果糖は、代謝される際にプリン体の分解を促進して、尿酸値を上げます。清涼飲料水や果物ジュースは控えましょう。生の果物は、ビタミンCや食物繊維が豊富であるため、尿酸値を上げません。
⑤尿酸値を下げる食品の利用
牛乳・乳製品、コーヒーは、尿酸値を下げる働きがあります。尿酸値が高い人は、低脂肪の牛乳がおすすめです。またビタミンCも尿酸値を下げるので、積極的に野菜を摂りましょう。
サプリメントにも要注意
健康食品やサプリメントの核酸やビール酵母などには多くのプリン体が含まれています。少量でも毎日摂ることで、摂取量が増えるので注意しましょう。
保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~
令和7年3月号に掲載
2025-03-10
【保健師だより】慢性腎臓病(CKD)
慢性腎臓病は、腎臓の機能が低下している状態です。糖尿病、高血圧、メタボリックシンドローム、喫煙、高齢等が原因で、腎臓の血管が痛み発症します。日本では、20歳以上の5人に1人が、その疑いがあると言われています。気付きにくく、進行すると透析治療が必要になります。
近年、慢性腎臓病対策が注目されています。
慢性腎臓病予防法
とにかく減塩
食塩を減らすと腎臓の負担が減ります。 汁物は1日1杯までにする、醤油やソースは、かけずに【つける】、漬物・ふりかけ・加工食品は控えめにする、食事は腹八分目にすることを心がけましょう。
脂質
悪玉(LDL)コレステロールは、血管を痛めるので120mg/dl未満を目指しましょう。菓子パン、乳製品(生クリーム、アイス、牛乳、ヨーグルト)、高脂肪肉、チョコレート、揚げ菓子は、悪性コレステロールを上げやすい食品とされています。
運動
有酸素運動は、血管がしなやかになり、腎機能の低下スピードが緩やかになります。1日10分多めに歩くことから始めてみましょう。
禁煙
喫煙は、血管を収縮させ、腎臓への血流が低下します。また、有害物質により腎臓の血管が傷つき腎機能低下を招きます。
肥満の解消
内蔵脂肪型肥満とメタボリックシンドロームは、慢性腎臓病発症・進行リスクが高まります。腹囲が男性85㎝以上、女性90㎝以上の方は生活習慣を見直しましょう。
保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~
令和7年2月号に掲載
2025-02-10
【保健師だより】健康に配慮した飲酒
2013年に〈アルコール健康障害対策基本法〉が施行され、その一環で2024年2月、日本初の〈飲酒に関するガイドライン〉が策定されたので、ご紹介します。
1.年齢の違い
高齢になると、肝臓の働きが弱まりアルコール分解が遅くなります。また体内の水分量も減るため血中のアルコール濃度が上がり、酔いやすくなります。
2.性別の違い
女性は男性と比べて、体内の水分量が少なく、分解できるアルコール量も少ないため、影響を受けやすいと言われています。その為、男性と比べて少量かつ短期間でアルコール性肝硬変になる恐れがあります。
3.体質の違い
アルコール分解酵素の働きの強さが、人によって異なります。働きが弱いと、顔が赤くなったり、動悸や吐き気、頭痛等(フラッシング反応)が起こる場合があります。分解酵素の強弱は、遺伝的要因により決まりますが、日本人の約4割は弱いタイプと言われています。
分解酵素が弱いタイプは、毎日飲酒を続けると、口腔がんや食道がんのリスクが高くなることが分かっています。強いタイプは、飲酒が習慣化しやすく、アルコール依存症のリスクが高くなります。実際に、アルコール依存症の9割がこのタイプです。
保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~
令和7年1月号に掲載
2025-01-10
【保健師だより】逆流性食道炎
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
今月は、逆流性食道炎についてご紹介します。
〈逆流性食道炎〉は、2000年頃から患者数が増えています。要因として、①高齢化、②食生活の欧米化により、高脂肪な食事を摂るようになり胃酸分泌が増えた、③ピロリ菌感染率の減少が考えられます。(ピロリ菌に感染すると胃酸分泌が減少するため)
〈逆流性食道炎〉は、胃液が食道に逆流することで、食道粘膜が炎症を起こします。炎症が胸焼け、逆流が酸っぱいものが込み上げる(どん酸)症状を引き起こします。
予防・改善策
【食事】
●食べ過ぎない
●食べてすぐ横にならない
●高脂肪食、アルコール、カフェイン、チョコレートには下部食道括約筋を緩める作用があるため避ける
【姿勢】
●背筋を伸ばす
※スマホを見るときは前屈み姿勢になりやすいので注意
●夜間は、逆流が起こりやすいため、クッション等を使い、胸から角度をつけて横になる
※酸っぱいものが込み上げてきたら、左側を下にしましょう。
【禁煙】
喫煙は、食道の運動機能を低下させ逆流を起こしやすくします。
【治療方法】
薬物治療で胃酸を抑えるのが基本です。重症の場合、食道に胃の上部を巻き付け逆流を防ぐ外科的治療もあります。
症状等、気になる方は、消化器内科を受診してください
保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~
令和6年12月号に掲載
2024-12-10
【保健師だより】バランス能力
日本理学療法士協会は、《高齢者は3秒に1人が転倒している》《高齢者は1分間に1人が骨折している》と発表しています。驚く数字ですが、皆さんは思い当たることないですか?
転倒と聞くと「たいしたことじゃない」と思う方もいるかもしれませんが、転倒が原因で介護が必要な状態になりやすいと言われています。発生場所としては自宅が最も多く、つまずき、滑り、踏み外しといった足元のトラブルで起こるケースが増えています。今月は、転倒原因の一つであるバランス能力についてです。
バランス能力チェック
①片足立ちテスト
両手を腰に添え、片足を5㎝程度上げ、姿勢を崩さずにいられる時間を計ります。
上げた足が床につく、上げた足が支えている足に触れる、支えている足がズレると終了です。時間は、60秒を上限とします。
15秒以内は転倒リスク、5秒以内は骨折リスクが高くなるため要注意です。
※転倒しないように、壁など支えのあるところで行ってください。
②5回立ち上がりテスト
40㎝の椅子から腕組みをして、5回立ち上がります。
15秒以上かかると転倒リスクが高くなります。手をつかないと立ち上がれない人は、更に高リスクです。
バランス能力アップ
片足立ち
片足立ちは、お腹やお尻、太ももなどの筋肉を鍛えることができます。左右1分ずつ、1日3回行うと、約50分間歩いた時と同レベルの負荷が股関節にかかる為、骨密度アップにも効果的です。
コグニサイズ
認知能力の低下も転倒の原因となっています。
コグニサイズは、国立長寿医療研究センターが開発した、運動と認知課題を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みの総称です。
例えば、ウォーキングをしながら、しりとりや計算を行う、座った状態で足踏みしながら3の倍数で手をたたくなどです。
普段の生活に取り入れてみましょう。
保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~