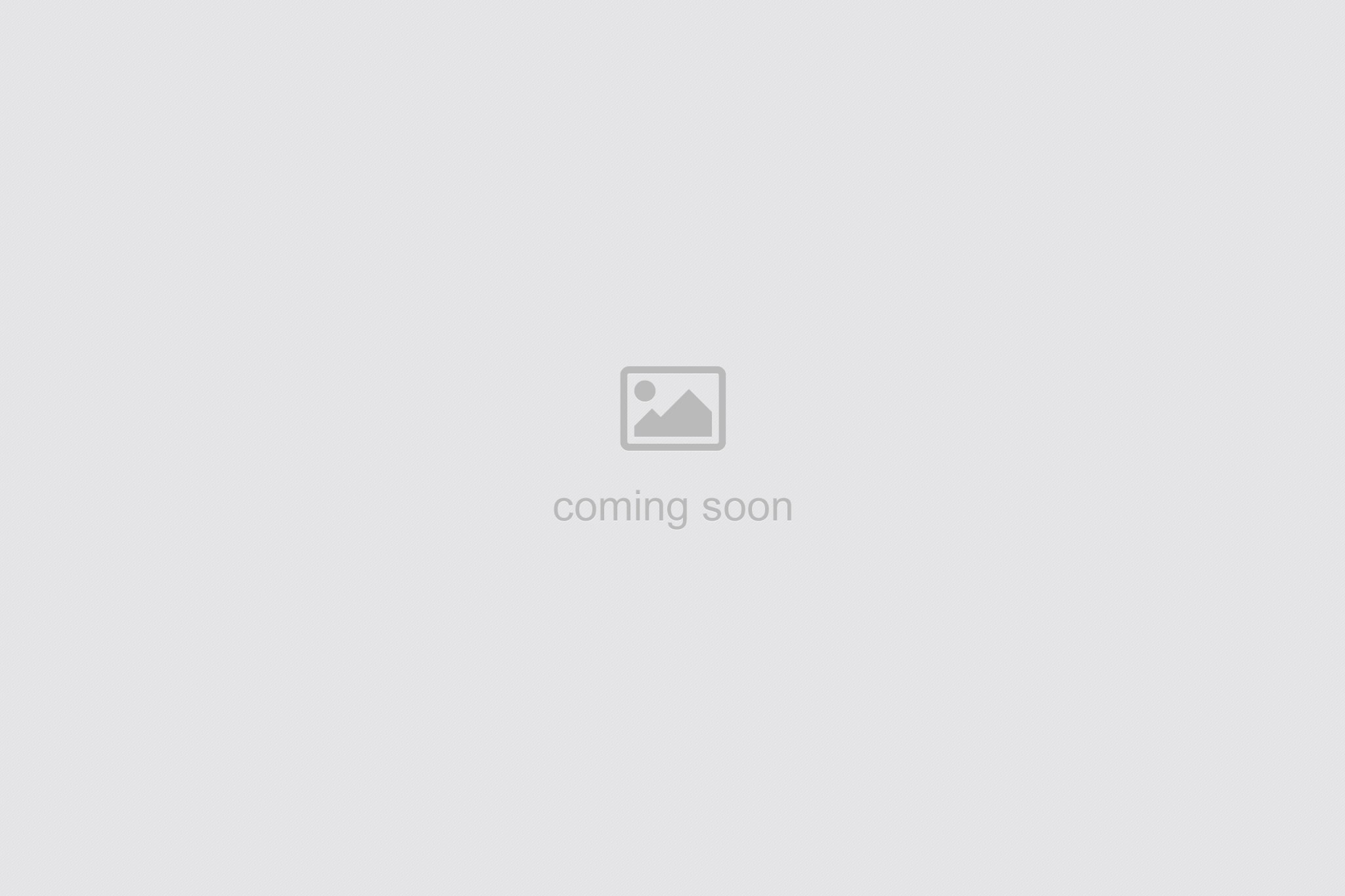毎月発行される香川県建設労働組合の機関誌「香川建設ユニオン」において、保健師による健康に関する記事を連載しています。
こちらでは、過去に掲載された記事をご紹介しています。
こちらでは、過去に掲載された記事をご紹介しています。
令和6年10月号に掲載
2024-10-10
【保健師だより】仮面高血圧
そもそも血圧ってなに?
血圧とは、心臓から送り出された血液が動脈内壁を押す力を指します。
血圧の高さは、心臓が血液を押し出す力と血管の広がりやすさで決まります。 血圧は一日の中で、常に変動しています。起床前から起床後にかけて上がり、夕方から夜にかけて下がり、睡眠中の血圧が最も低くなります。
高血圧の原因
過剰な塩分摂取、過剰飲酒、野菜や果物の摂取不足、喫煙、ストレス、遺伝、肥満が関係しています。
仮面高血圧に注意
【仮面高血圧】は、健康診断や病院では正常なのに、家や職場、早朝、夜間などで血圧が高くなることを指します。病院では正常血圧のため、発見されにくいですが、脳血管障害や心筋梗塞、突然死を発症する危険が高いことが分かっています。
仮面高血圧は、高血圧を呈する時間帯別に3つのタイプがあります。
【早朝高血圧タイプ】
早朝血圧が135/85mmHg以上で診断されます。夜間から高血圧が持続しているタイプと、早朝に急激に血圧が上がるモーニングサージタイプがあります。
【昼間高血圧タイプ】
昼間の血圧が135/85mmHg以上で診断されます。精神的・身体的ストレスは血圧に影響することが分かっており、昼間高血圧の一つとして〈職場高血圧〉があります。
【夜間高血圧タイプ】
夜間血圧が、120/70mmHg以上で診断されます。
通常夜間は、身体を休めるため、日中と比べて約10~20%血圧が下がります。しかし、夜間高血圧は血圧が高い状態が続くため、身体に大きな負担がかかります。
仮面高血圧を見つけるために、自宅で血圧測定をしましょう。
血圧の測定方法
●起床後1時間以内
●朝と晩(就寝前) 2回測定
●朝は食前、服薬前、 排尿後
●2回測定して平均 値をとる
《注意点》
①背筋を伸ばして測る
②腕帯の高さを心臓の高さに合わせる(手首式でも同様)
③測定中は話さない
④厚手の服は脱ぐ いかがでしたか。日本高血圧ガイドラインでは、高血圧の判定は診察室血圧よりも家庭血圧を優先すると定めています。この機会に血圧測定を始めてみませんか。
保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~
令和6年9月号に掲載
2024-09-10
【保健師だより】保健師だより~歯と口の健康~
保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~
令和6年8月号に掲載
2024-08-10
【保健師だより】夏バテ改善法
暑さで食欲が落ちたり、身体がだるいと感じたりしていませんか?その症状、夏バテかもしれません。
夏バテとは、暑さに身体が順応できず自律神経が乱れたり、脱水や栄養不足によって身体の不調が起こる総称です。
症状は、倦怠感、疲れがとれにくい、イライラする、意欲低下、食欲低下、体重減少などで、ゆっくり進行します。
熱中症は暑さで体温が上昇し、脱水となり、頭痛、吐き気、こむら返り、まっすぐ歩けないなどの症状があります。一日で急激に進行し、重症化すると臓器が壊れ、死に至ります。
夏バテになりやすい生活習慣
①睡眠不足
睡眠不足は自律神経が乱れます。また、睡眠の質が下がり、疲労が回復しにくくなります。
②運動不足
運動不足は、筋肉が減ります。筋肉には、水分が蓄えられており筋肉が減ると体内の水分量が減り脱水になりやすくなります。
③冷たい飲料をよく飲む
冷たい飲料を摂りすぎると、胃腸の動きが低下、胃液も薄まり、消化不良や食欲低下に繋がります。
④冷房を低い温度にしている
冷房の効いた部屋と外の行き来による急激な温度変化が起こると、自律神経が乱れやすくなります。
⑤食事内容が偏りがち
食事のバランスが偏っていると、栄養素が不足し、疲れやすくなります。
夏バテ解消法
【ビタミンB1】
だるさや疲労感を感じる時は、ビタミンB1が不足している可能性があります。
ビタミンB1は、豚肉、うなぎ、玄米、ごまに多く含まれています。
【クエン酸】
クエン酸は、疲労回復におすすめです。お酢、うめぼし、グレープフルーツ、キウイ、レモン、ゆずなどに含まれる酸味成分です。
【運動】
適度な運動は、自律神経のバランスを整えます。ハードな運動は、交感神経の働きを過剰にし、逆効果となります。ウォーキングやヨガ、ストレッチなどゆっくり深い呼吸をしながらできる運動をしましょう。
【睡眠】
40度のお風呂に10分程度浸かったり、目の周りを温めるとリラックス効果があり、眠りやすくなります。寝具を、綿や冷感素材に変えるのもおすすめです。
【気温差をなくす】
外気温と室温の差は5度以内が身体に負担が少ないと言われています。エアコンは26~28度の設定にしましょう。
保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~
令和6年7月号に掲載
2024-07-10
【保健師だより】がん予防をはじめよう
先月号に引き続き《がんを防ぐための新12ヵ条》についてご紹介します。
【9条】
ウイルスや細菌の感染予防と治療
〈肝炎ウイルス〉
B型・C型肝炎ウイルスに感染すると、肝がんになりやすいことが分かっています。血液検査で肝炎ウイルスの有無が調べられます。
〈ヒトパピローマウイルス〉
子宮頸がんは、性交渉によるヒトパピローマウイルス感染が原因で起こります。
17歳までに子宮頸がんワクチンを接種すると発症率が88%減少したという研究結果もあり、国は令和3年から積極的勧奨を再開しています。
現在、子宮頸がんワクチンの定期接種を逃した方や未完了の方にキャッチアップ接種をしています。平成9年~平成19年生まれの女性が対象で無料です(令和7年3月31日まで)詳しくは、住民票のある自治体へお問い合わせください。
〈ピロリ菌〉
ピロリ菌は、胃がんのリスクを高めます。ピロリ菌検査を受け、感染していれば除菌治療を受けましょう。
保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~
令和6年6月号に掲載
2024-06-10
【保健師だより】がん予防をはじめよう
2人に1人が一生に一度は、がんに罹患するというデータがあるほど、がんは身近な病気です。その一方、多くの研究により、がんは予防できることが分かっています。
【がんを防ぐための新12ヵ条】
4条
バランスのとれた食生活を
赤肉(牛・豚・羊など)や加工肉は大腸がんのリスクを上げるため、週に500gまでにしましょう。また、飲食物を熱い状態で摂ると食道がんのリスクが高くなるので控えましょう。
5条
塩辛い食品は控えめに
塩分摂取量を抑えることは、胃がん予防に有効です。
6条
野菜や果物を摂取
野菜・果物の摂取は、食道がん、胃がんの予防になります。
7条
適度に運動
身体活動量が多い人ほど、がんの発生リスクが低くなります。特に、男性は大腸がん、女性は乳がんのリスクが低下します。
8条
適切な体重維持
肥満とがんは、強い関連がないことが示されていますが、やせによる栄養不足は免疫力を弱めます。 男性の適正なBMI値は、21~27、女性は21~25です。この範囲内で体重管理をしましょう。
続きは、来月号に掲載します。
保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~