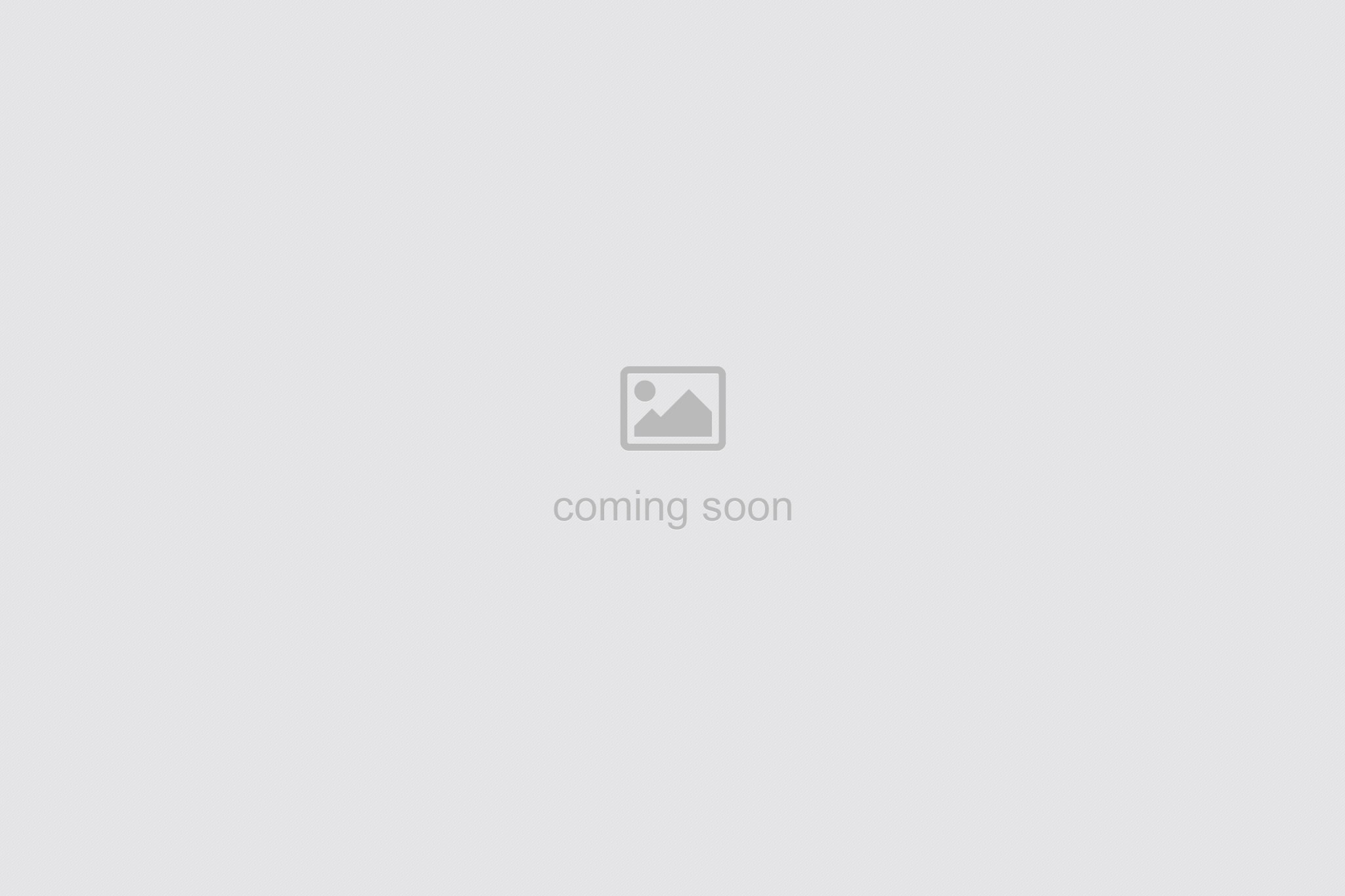令和3年6月号に掲載
2021-06-01
【保健師だより】健康寿命をのばすポイント
日常生活を送るのに介護を必要としない期間を健康寿命といいます。先月は一つめのポイント〝喫煙〟についてご紹介しました。今回は〝飲酒〟についてご紹介します。
健康を左右する10項目
- 飲酒
- 節度のある飲酒
節度のある飲酒とは、体に負担がかからない飲酒量をいいます。男性はアルコール量で約23グラム(日本酒1合程度)、女性は男性に比べ肝臓が小さいので男性の半量が適量とされています。たまに飲む場合でも、一時に大量に飲むと体に大きな負担がかかります。適量内の飲酒をお勧めします。 - 休肝日をつくる
アルコールは人体に有害な物質が含まれています。有害物質は肝臓で分解されますが、分解することで肝臓はダメージを受けます。休肝日をつくると肝臓を休ませ、ダメージを回復させることが期待できます。
また、お酒を我慢する習慣が身につくので、アルコール依存症の予防にも効果的です。週2日程度、休肝日をつくることが推奨されています。 - 寝酒は避ける
アルコールは催眠作用があるので、寝つきは良くなります。しかし、日本酒1合程度のアルコールを分解するのに2~3時間かかるので、寝酒をすると睡眠中にアルコールの分解が行われ、睡眠の質が低下します。また、アルコールが分解されると脳が覚醒するので、睡眠後半の眠りが浅くなります。さらに、アルコールの催眠作用には耐性があるため飲酒量が増えやすくなり、お酒がないと眠れなくなったり、アルコール依存症になる恐れもあります。良質な睡眠のためには、就寝の3時間前までに飲み終えましょう。 - 飲まない(飲めない)人にお酒を強要しない
アルコールの分解に関わる酵素の働きは、遺伝で決まっています。日本人の約半数は酵素の働きが弱いと言われています。少量の飲酒で赤くなる人には、お酒を強要しないようにしましょう。

保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~