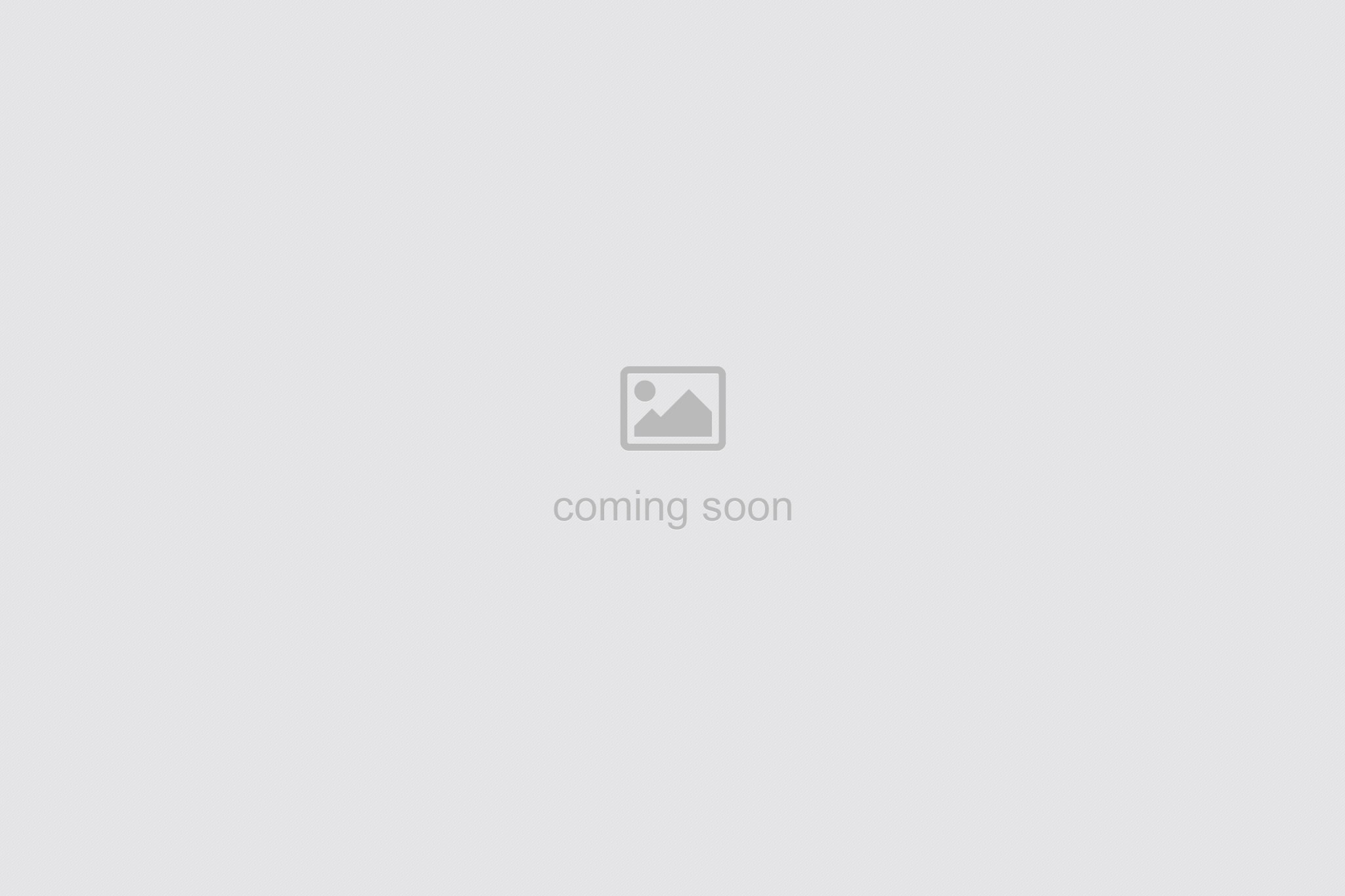令和元年8月号に掲載
2019-08-01
【保健師だより】早食いをやめるといいことだらけ?脱早食いに挑戦!
平成21年度の国民健康栄養調査では、男女ともに肥満度が高い人ほど、早食いであるということが分かっています。
食事をすると、血液のブドウ糖濃度が上昇し、満腹中枢がそれに反応して満腹感を知らせます。ブドウ糖の濃度が上昇するには、ある程度の時間が必要であり早食いの場合、脳が満腹感を感じる前に多くの食事をとってしまい、摂取エネルギーが多くなり、肥満に繋がります。
食事をすると、血液のブドウ糖濃度が上昇し、満腹中枢がそれに反応して満腹感を知らせます。ブドウ糖の濃度が上昇するには、ある程度の時間が必要であり早食いの場合、脳が満腹感を感じる前に多くの食事をとってしまい、摂取エネルギーが多くなり、肥満に繋がります。
ゆっくり食べる効果

- ダイエット
よく噛んで食べると、食べ過ぎを防ぐことができます。噛む回数を10回と35回で比較した研究では、35回噛んだ方が満腹になるまでの食事量が減少したという結果が出ています。 - 脳の発達
よく噛むことは脳細胞の働きを活発化します。あごを開けたり閉じたりすることで、脳に酸素と栄養を送り、活性化します。高齢者は認知症予防にも効果があります。 - 味覚の発達
よく噛むことで、食べ物本来の味が分かり、味覚が発達します。食材そのものの持ち味を味わうように心がけましょう。 - 虫歯、歯周病予防
噛むことで、唾液分泌がよくなります。唾液には抗菌作用があり、虫歯や歯周病を防ぎます。 - がん予防
唾液に含まれる酵素ペルオキシダーゼには、食品中の発がん物質を抑制する働きがあります。
よく噛んでゆっくり食べるコツ
食べる早さは、噛む回数で変わります。1口ごとに30回は噛み、最低でも20分かけて食べるのが理想的です。
噛む回数が30回というのは、食べ物と唾液が最もバランス良くまとまり、飲み込みやすいという研究から来ています。
噛む回数が30回というのは、食べ物と唾液が最もバランス良くまとまり、飲み込みやすいという研究から来ています。
- 調理の工夫
調理する際、食材は大きく、厚めに切り、噛みごたえがある状態にしましょう。魚やお肉は骨付きのものを選ぶと、噛みごたえや食べにくさから時間をかけて食べることができます。 - 一口量を減らす
一口量が多すぎると口の中が一杯になり、あまり噛まないうちに飲み込んでしまいがちです。一口量を少なくすると、噛む回数が1.3~2倍増えたという研究結果も出ています。 - 噛み方を変える
右側で5回、左側で5回、もう1度繰り返し、最後に両方の歯で10回噛みます。
これは、日本咀嚼学会が推奨している効果的な噛み方です。
難しければ、今より10回多めに噛むように心がけましょう。
いかがでしたか。どの方法も、今日から実践できる方法です。この機会に食事の取り方を見直してみませんか。
保健師への問い合わせ先:TEL:087-866-4721
~健康に関するご質問、ご相談について、お気軽にご連絡ください~